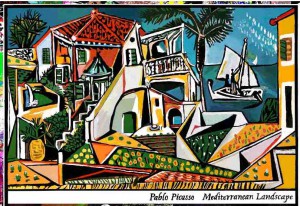さっき、夏目漱石の「門」をぱらぱらめくっていたら、最初の方で、宗助が散歩に出かけ、切手と「敷島」を同じ店で買って手紙を出したあと、そのまま帰るのも面白くないんで
「咥え煙草の煙を秋の日にゆらつかせながら、ぶらぶらと歩いているうちに」
という文に出くわした。ところで先の「敷島」はその当時の煙草の銘柄である。これを読んでなんだか一気に明治に逆戻りするような気がした。当時は人通りもまばらで、往来は適当に汚れていて、煙草をふかしながら歩いて吸殻を道にもみ消しても、特段の問題はなかった時代だったのだろう。もっともそれならば明治まで戻る必要もなく、昭和のころもそんな感じだった。
僕はここしばらく、昭和初期の日本映画をよく見ることが続いたのだけど、当時の人がいかに煙草をやたらと吸っていたか見てあらためてびっくりする。なにかというと煙草に火をつけて、あたりが煙っている。当時は満員の通勤電車の中でも平気で煙草を吸っていたって、現代の朝の通勤電車で、エンジンの音だけが流れて皆が静まり返ってじっとしている車内から想像できるだろうか。しかし変われば変わるものだ。
思えば、僕が学校を出て就職した職場でも、当時は煙草を吸う人のめいめいのデスクには灰皿があって、仕事しながらふつうに煙草を吸っていた。打ち合わせの部屋はみなが煙草をやたらと吸うもんだからけっこう煙っていたものである。数えてみると今から20年ぐらい前はまだ、そうだったのだ。
それにしても、この煙草については本当に世の中変わった。しかも世界的に煙草を廃止する方向に動いているので、タバコ吸いにとっては、あらがいようがない現実である。もっとも日本でも外国でもまだ煙草はふつうに売っているし、けっこうな人が吸っているし、喫煙者は建物を始めいろいろなところから追い出されてはいるものの、喫煙所へ行けば、まだけっこうたむろしてはスパスパ吸って去って行く、という光景はなくなっていない。
冒頭の漱石の描写で、彼が往来に設置された灰皿で煙草をもみ消すはずもなく、当然のように道端にポイっと捨てて足でもみ消したはずであろう。いわゆる「吸殻のポイ捨て」である。現代では特に、煙草については、その存在自体が悪者扱いされているのも手伝って、吸殻ポイ捨て行為は二重に悪い行為に写る。知っての通り、ところによっては、警官に見られればその場で罰金まで取られる。吸殻はちっぽけで小さいので、ポイ捨て行為だけとると些細なことだと思うのだけど、煙草だけは特別のようである。
ところで僕はどうかと言うと、煙草は止めてはいないが今ではもうほとんど吸わなくなった。ただ、なんらかストレスな仕事をしたり、ライブバーで演奏したり、というときに限って、ごくたまに吸う。平均してならしてしまうと1日で1本を切ってしまうので、もう、「吸わない人」と言ってもいいかもしれない。
しかしときどきは、吸うのである。それで自分の喫煙マナーはあまりよくない。灰皿のあるところで吸うときはいいとして、外に出ていて煙草が吸いたくなると、まず周りを見回して喫煙所が運よくあればそこへ行って吸うが、たいていは見つからないので、人があんまりいない路地かなんかに入ってそこでプカプカやっている。で、吸殻はその場に捨ててもみ消すので、立派な吸殻ポイ捨て行為であり、見つかれば罰金ものというわけだ。
自分がそうなので、他人が吸殻ポイ捨てしていても何とも思わない。しかし実は、自分が吸殻ポイ捨てするときにはけっこう後ろめたさを感じながらやっている。道で煙草に火をつける段階からそれを感じるので、公共の場で煙草を吸うことについてもなんらか罪悪感を感じているようである。加えて最後に道にポイっと捨ててもみ消し放置するときは、喫煙にポイ捨てが加わってほぼ2倍の罪悪感というわけだ。そんなに後ろめたいなら吸わなきゃいいのに、と思うが、その時その場で吸いたいんだからしょうがない。
では、なんでそんな罪悪感を感じるか、というと僕の場合はわりとはっきりした理由があり、幼少のころ、死んだ親父に公共マナーについてこれでもかというほどうるさくしつけられたからである。まず、どんな小さいゴミであろうとゴミ箱以外の公共の場に捨てるのは絶対だめ。さらに、公共の場に落ちているゴミを見つけたら必ず拾ってゴミ箱に捨てること。この二つにつき、親父と一緒に外を歩いているときは必ず徹底されたのである。
幼少のしつけというのは怖いもので、その後、青年になり、多少のゴミなどは道にポイする若者ノリになったときでも、なかなかゴミを道に捨てられなかった。たかが道にポイっとするだけなのに、大げさで馬鹿げているが、けっこうな勇気を要する、という風であった。これがそのまま続いているわけで、したがってしつけから40年近くたった今でも、公共の場での喫煙と吸殻ポイ捨てについて罪悪感を感じるという始末である。
ところで今から20年ほど前、スペインのマドリッドへ旅行したとき、スペイン人たちのゴミのポイ捨てのすごさに感動したことがある。ゴミの大小を問わず、誰もが道や広場やそのへんに捨てるので、往来も広場もゴミだらけである。煙草に至ってはそんなちっぽけなものは屁でもないとばかりに、みな歩き煙草をして吸い終わるともみ消しもせずそのままポーンと往来に投げ捨てる。そしてさらにびっくりしたのが街にたくさんあるカフェのバール(BAR)である。食ったり飲んだりするところなのだが、出たゴミはすべて躊躇なく床に捨てる。なのでバールの床はゴミだらけで足の踏み場もない。で、定期的に店の人が掃いて捨てている。実は往来に散らばるゴミもそうで、いちおう定期的に清掃員のじいさんが掃いて捨てている。
このマドリッドは僕にとっての初めての海外で、このゴミに対する態度に、もうけっこう誇張でなく感動した。ゴミを道にポイ捨てするのに勇気がいるほど罪悪感を感じている僕は、スペイン人の、いい加減さ、おおらかさ、そしてある意味合理的な行動に、本当に感心したとともに、憧れたものである。しかしながら、日本に帰ってきてしまうと、スペインの習慣をそのまま持ち込めるわけもなく、元の自分に戻ってしまうのであった。
自分はスペインを皮切りとして、ヨーロッパ、アジア、アメリカと、かなりの回数、そしてかなりのたくさんの国へ出かけているのだが、自分が見た限り、このゴミのポイ捨てマナーについては日本が断トツにうるさく、そして徹底している。自分の経験からいえば世界一であろう。最近でこそ、いろんな国が日本に追い付いてきたが、たぶんいまだに日本は世界一公共の場がきれいな国だと思う。
そういえば、シンガポールではどんな小さいゴミであろうと往来に捨てたとたんに罰金であり、ガムを捨てただけで信じられないぐらいの金を取られるので、街は異様にきれいだ、と聞いたことがあった。これを聞いて、へーえ窮屈な国だな、と思ったものだったが、少し前に実際にシンガポールへ行ってみたら、道端にはふつうにゴミが落ちているし、歩き煙草で吸殻ポイ捨ての人がふつうにたくさんいて、なんだ、と拍子抜けしたことがある。たしかに法律は厳しいのだけど、みな、あまり厳格に守らないようなのである。
さて、以上、実はもっといくらでも話はあるのだが、このへんにしよう。
自分としては以上の経験から、日本を基準にせず世界を基準にすれば、ポイ捨てはまだまだふつうの行為なので、ポイ捨てなんて少しであれば別にいいんじゃないか? という態度である。さっき書いたマドリッドのやり方のように、みんなでポイ捨てして、それで定期的に掃除する方が、むしろ合理的なんじゃないかと考えたりする。
で、この前、ツイッターでなにげなく「ポイ捨てぐらい別にいいじゃん」とツイートしたら、さっそく知人からリプライがあり、ポイ捨てはダメ、とあり、そしてそういう行為は「社会に甘えている」と書いてあった。
実は、この「社会に甘えている」という言葉がものすごく新鮮だったのでこれを読んで思わず、うわー、っと反応してしまった。思えば自分はこの「社会に甘える」という考え方をずっと長い間忘れていた。ポイ捨ての是非について考えるとき、社会に甘えるという考え方をするということが自分には新しかったので、「皮肉ではなく、素直に、その考え方に感心しました」、とかなんとかリプライした。あと、この「ポイ捨てしている人は社会に甘えている」という考え方も、僕にも読んですぐに理解できた。なので自分も知ってはいたのだ。しかしながら改めて、なぜ「ポイ捨て行為は社会に甘えた行為」なのだろう。
自分の勝手で公共の場にポイ捨てし、捨てられたゴミについて自分は責任を持たず、しかも捨てられたゴミを社会の他の成員が見つけたときにすでに捨てた本人を特定できないので責任追及が不可能になる。つまり、捨てる人は、自身の責任放棄と、他人の責任追及から逃げる、という二重の悪いことをしているということなのだろうか。そして、ポイ捨てされたゴミが溜まれば最終的にどうしても処理しないといけないくなるので、誰かがその役を引き受けることになる。ポイ捨てしている人は、自分の属している社会の誰か他人にゴミを押しつけて自らは知らん顔をしている、という意味で「社会に甘えている」ということになるのだろうか。
「甘えている」というのは、主に子供に対して使う言葉だろうが、子供であれば、自分のやりたいことをやって何らか問題になっても「親がなんとかしてくれる」ということを「甘えている」と言うのであろう。なので社会に甘えているというのは、自分のエゴでなんか社会に問題を引き起こしても「社会がなんとかしてくれる」と考えることを言うのであろう。
自分はおそらくほぼ以上のように理解していたのだと思うので、「ポイ捨ては社会に甘えている」という発言を読んですぐ分かったのである。しかし、上述の理屈で本当に合っているかはどうもあんまり自信がない。というか、上述、歯切れが悪い。自分の不得意なことについて書いたり考えたりするとこうなるのであろう。
しかしながら、また冒頭の漱石の小説の時代のポイ捨て事情を思い出してみると、それでは当時の人たちが社会に甘えていたかというとそうでもない。昔の日本も、スペインも、あるいは他の国も、ポイ捨てのゴミは定期的に誰かが清掃して、それでうまく回っていたわけだ。それがうまく回っている限り、ポイ捨て行為は社会に甘えた行為である、ということにはなっていなかったということだろう。それでは、どこがその転換期になるのだろう。
いちばん端的な理由は、社会の人口がかつてよりずっと増え、さらに消費行為が増え、いわゆるゴミ自体の量が増加し、その結果、みなのポイ捨てのゴミが社会で処理しきれなくなるほど大量になってしまったということがあるだろう。最近だと、イタリアのナポリでこれが起こったそうで、ちょっと前聞いた話だと、ナポリの街は処理しきれないゴミの山であちこちがふさがって大変なことになっていたそうである。
このような極端に破局状態になると、もうポイ捨ての習慣もみなが自覚して止めない限り、収拾がつかなくなる。それが分かってもポイ捨てを止めない連中は、社会に甘えていることになるであろう。しかし、先の子供の例でもわかるように、子供が自分が親に甘えているのを自覚しないのと同じく、ポイ捨てを平気でする輩は自分が社会に甘えているなどという自覚は無いのがふつうで、他人や社会のことなど一切考えず、自分がやりたいようにやっているだけだろう。しかも、その人数はなかなか減らないだろう。結局のところ、社会はこの手の「社会に甘えている無自覚な輩」を一定数かかえていないといけないことになるだろう。
あともう一つは、ゴミの落ちていないクリーンな街を社会が望んでいる、というのもある。おそらく日本はこっちである。この場合、ポイ捨ての無い社会を望むわけだが、思うにこれは意外と説得力がない。たとえば僕のように、「オレは別に道にゴミが落ちててもいいよ」、という人々に対してどうやって説得すればいいか。これは、仕方ないので、あの手この手であろう。最近の東京で言えば、公共の場で煙草を吸って吸殻をポイ捨てすることがいかに「いけない行為」であるかということについて、次から次へとよくこれだけ思いつくもんだと思うぐらい理由を見つけて、それを一つ一つポスターにしてそこらじゅうに貼っている。たとえば、他人は煙を嫌がっている、煙草の火は700度、しかも歩き煙草の火は子供の背丈の位置にあり危険、吸殻は下水に入り込み詰まりを引き起こす原因、云々と、いくらでも出てくる。
さっき、「社会はこの手の社会に甘えている無自覚な輩を一定数かかえていないといけない」と書いたが、この厄介な輩は実はかなりたくさんいる。そして容易なことで数は減らない。なので社会の残りのメンバーは、この厄介な輩の面倒を見ることを強いられる。これは不公平だし、第一そんなやつらの面倒は見たくないし、それら厄介な輩が社会的責任を自覚する自分たちのようになってくれれば面倒は減るのに、自分たちに甘えていることを自覚することすらないのは何ということか、と不平はたくさんあるだろう。こういう事情は、ここで書いているポイ捨てに限ったことではなく、多岐に渡っていると思う。
というわけで、社会的責任を自覚している社会の上の方の人々は、この問題を処理するために(ここでは再びポイ捨てに話を限るが)、さまざまな理由を見つけ出して先の東京のポスターのように下の方の人々を啓蒙しようとする。ただこれらの理由はいずれも小粒であって、見ればなるほどと思うことではあるが、それほど大きな「社会的問題」には見えない。逆に小粒な身近な問題じゃないとそれらの輩には理解できないというのもある。したがって啓蒙には根気がいる。繰り返し繰り返し、いつでも同じような小粒な問題を次から次へと投げつけて、それを止めることなく続けていないといけない。
ここまで来ると、実は、さっきのナポリの問題と実は本質はあまり変わっていないことが分かる。やはり、結局は、ゴミが処理できなくなることを予想しているのであろう。ナポリのような惨憺たる状況になる前に手を打っている、とも言える。しかしながら、このような行動は「政治家の仕事」であって、われわれ一般市民の仕事と言えるだろうか。ゴミの量と処理可能な量を算定してそのバランスを見ながら事前にゴミをコントロールする計画を立て実行する、というのはこれはどうあっても政治の仕事である。
この政治家のやっている仕事の道筋をまとめると、「ポイ捨てが平気で、社会に甘えている輩が相当数いて、しかも容易に数が減らない」、「一方、その輩の面倒を見たくもないのに見ないといけない社会の上の方の人々の不満がある」、「困った輩たちを自分たちのところまで引き上げたいが無自覚な輩たちにそれを自覚させるのは至難の技」、「仕方ないからポイ捨てが悪な理由を大量に常に輩に投げつけ、少しでも全体を改善する」、「ただしその理由は馬鹿でもわかるぐらいの小粒なものにしないといけない」、「さらにしつこいぐらい繰り返し同じことを忠告しないといけない」、となり、なかなか煩雑な戦略である。もっともごく普通にどこでも行われている戦略でもある。
以上が政治家の仕事だが、この煩雑な仕事を、今度は政治家ではない市民の言葉に翻訳すると、それが、「クリーンな街を望む」ということになるのではないだろうか。
政治家から見ると、社会の上の方の多くを形作る良識層が「クリーンな街を望む」という一種の道徳的感覚のようなものを持ってくれることはとても重要なことで、仕事は格段にやりやすくなるはず。クリーンな街をみなが目指すことで、社会が自動的に自己組織して、浄化作用が働いて、特に厄介な繰り返し政策をしなくとも、面倒なゴミ問題が解決するならこんなにいいことはない。
こと日本におけるクリーンな街の実現については、以上の作戦がきわめてうまく働いていると思う。そして、僕の感覚だと、それを通り越して、「うまく行き過ぎている」のだ。というのは、自分には、日本の社会の良識層が、あまりに無自覚に、「クリーンな街は素晴らしい、日本が世界に誇れることだ」と感じていて、ときにそれが高じて「汚い国は醜い、民度が低くて劣っている」、というところに発展しがちなのが見えるからだ。
社会の感覚がここまで来てしまうと、そこにはどうしても「相互監視」の感覚が現れる。「クリーンな街を望む」という民意に反する人間に対して、国が警告するのではなく、市民が進んで警告するようになる。お互いが警告を発して、目に見えることから目に見えないことまで、反する人間に圧力をかけることが常態化する。大半の人は別に相互監視の社会に生きていても特段に窮屈さを感じないのだろうし、それによって自分たちの生活が厄介な輩に妨害されることなく快適に生活できるようになるわけだから、別にかまわないのだろう。
自分について言えば、僕は、そういう社会の良識層を常に疑っていて、自分は極力そうならないようにしている。しかしながら自分が属している層は明らかにその良識層の方で、ポイ捨てして平気な厄介な輩側ではない。前に書いたように煙草のポイ捨てていどでやましいと感じる自分が、厄介な輩側の仲間になれるはずがない。結局、自分の立ち位置はけっこう中途半端である。でも、それで構わない。
自分のような人間は、厄介な輩たちはそのままにして、むしろ、「無自覚にクリーンな街を望む」という良識層の人々を相手に、この文のようないい加減な屁理屈をこれからもずっと言い続けることになるのだろうなと、最近、思う。それを自分の社会での立ち位置にしよう、と思うのである。あまりに長くなってしまったが、この文では、本当は、「社会に属する個人は、その社会を擬人化したとき、それをどう見るか」みたいな話にしたかったのだけど、書いたらそうならなかった。それについては、またいつか。